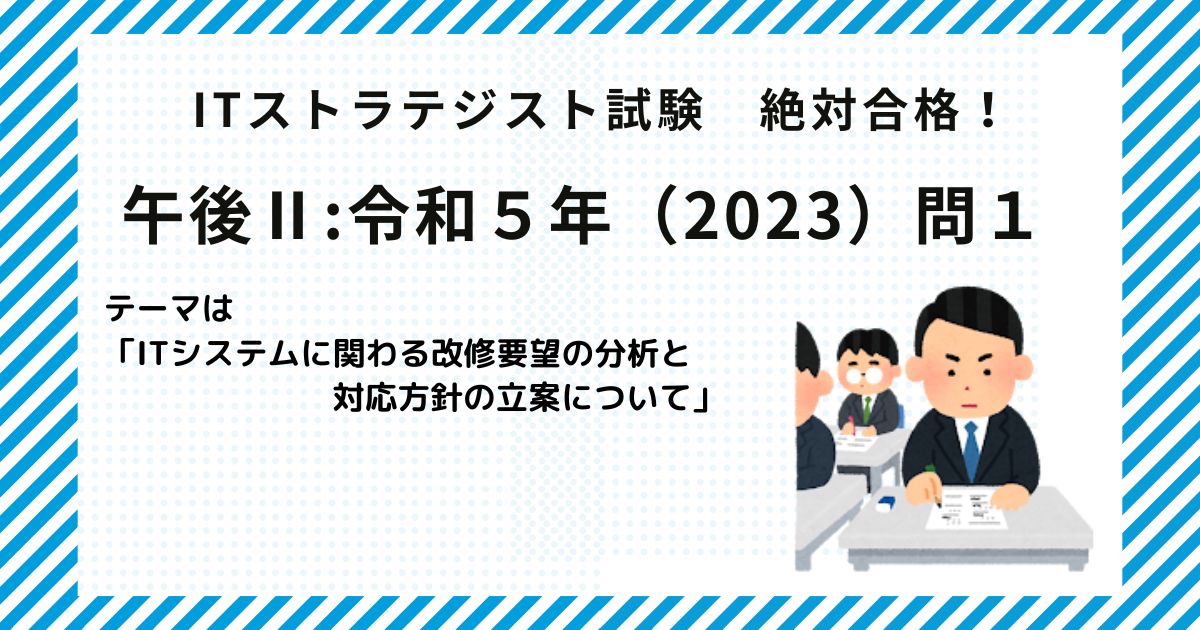ITストラテジスト試験午後Ⅱ(論文)対策です。今回から2023年(令和5)開催の試験問題を題材にしていきます。まずは問1。「改修要望の分析と対応方針の立案」の問題です。
こんにちは!セイジュン@エンジニア応援隊(@39Seijun)です。
午後2対策の「論文の骨組み、プロット作り」、今回から2023年(令和5)の問題をやっていきます。まずは問1から、テーマは「改修要望の分析と対応方針の立案について」の問題です。
論文の解法については、こちら午後Ⅱ対策でまとめました。過去問:令和5年春試験:ITストラテジスト区分の午後Ⅱ問題、こちらIPAサイトから引用しております。原典も是非ご参照下さい。
令和5年春試験:ITストラテジスト区分の午後Ⅱ問題(問1)
さて、問1。タイトルは「ITシステムに関わる改修要望の分析と対応方針の立案」です。まだ問2、3と見ていませんが「この問1は取り掛かりやすいテーマだな。この問題を選択するのがいいかもな」というのが第一印象です。
ITストラテジストを受験される皆さんの経歴・キャリアパスはどういったものでしょうか。
IT業界のキャリア15年以上で、初手はプログラマから入ってSEとなり、経験を積みながら社内の職階も上がり、サブプロジェクトを任されてプロジェクトマネージャも経験した。PMを極める道や、基盤系などの技術寄りに行く道もあったが、顧客・ユーザー・経営とのコミュニケーションにも関心があって、より上流工程への関わりが増してきているというところかなと思います。
もちろん、ユーザー企業に在籍されていて、IT部門や経営企画部門に属しながらITストラテジスト資格を取得しようとされている方もいらっしゃると思いますが、割合的には前者が多そうです。
そうした場合、新規のシステム構築と同様に、あるいはそれ以上に既存システムの保守・運用および改修の経験が豊富な方が多いかと思います。実体験を基に、論文記述を始めることができるという観点から、この問1は親近感のある問題と言えるかも、です。
いきなり話がそれてしまいました。問いに戻りましょう。
本文の読み解きは後ほどとして、まずは設問ア~ウから論文のプロットを組み立ててみましょう。
まずは、設問ア~ウを以下、抜粋します。
設問イ 設問アで述べた改修要望に対して、あなたはどのような情報を収集し、どのように分析し、どのような問題の真因を特定したか。工夫したこととともに、800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
設問ウ 設問イで述べた問題の真因について、あなたは利用部門や関係部門とともに、どのように協議し、どのような対応方針を立案したか。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
さて、今回も、本文を読む前に、論文の骨組み(プロット)は、設問ア~ウで導いてみましょう。設問での文字数指示から凡その文字数も補記してみます。
以下、です。
1.私が携わったITシステムの改修要望の分析について・・・設問ア(800字以内の指示に対して、750字を想定)
1.1.事業概要と分析対象業務・システム(250字)
1.2.利用部門からの改修要望(250字)
1.3.利用部門の問題認識(250字)
2.改修要望に対する情報収集・分析・真因の特定・・・設問イ(800字以上1,600字以内の指示に対して、1,200字を想定)
2.1.改善要望に対する情報収集(400字)
2.2.改善要望の分析(400字)
2.3.問題の真因特定(400字)
3.関係部門との協議と対応方針の立案・・・設問ウ(600字以上1,200字以内の指示に対して、800字)
3.1.利用部門・関係部門との協議(400字)
3.2.改修要望に対する対応方針の立案(400字)
どうでしょう。おおよそのバランス、こんな感じではないでしょうか。
では、本文にいきましょう。冒頭、「昨今のITシステムは、(中略)様々な改修要望が上がってくる」と始まります。続いて、1つの段落を使って以下の論旨展開が進みます。
「改修要望は、利用部門の視点だけで検討した部分的な内容にとどまっている可能性あり。ITストラテジストは、利用部門の問題認識や、①現状の業務プロセス②ITシステムの機能③利用状況などの情報を収集、客観的現状分析を行う。」
その後、「収集・分析を行う際には、次のような全社視点で多面的分析を行うことが重要」として、箇条書きを4点、続けます。
論文問題の問い文章において、箇条書きが出てきたら、ほぼほぼ具体的事例を列挙してくれています。論文のコアを形づくる設問イにマッピングできるように誘導してくれていると言い換えてもいいかなと思います。見ていきましょう。大幅に要約します。ぜひ原典に当たってください。
・利用部門の問題認識が部分最適になっていないか
・他の事業部門のサービス・業務に関連する、同様の問題・改修要望はないか(横展開)
・バリューチェーンの上下流に、この改修要望に関連する問題がないか(上下展開)
・利用者・運用者・顧客・取引先等に、この改修腰部に関連する問題+他の改修要望はないか(人の目線)
以上が箇条書きの4点。結びに、「さらに」という枕詞をつけて、「特定した問題の真因解消に寄与する解決手段・スケ・体制・投資効果などを利用部門・関係部門と協議し、対応方針として立案」と結びます。ラストの部分は、【改修要望の分析】ではなく、【対応方針の立案】部分にかかってくるので、そのまま設問ウのヒントになっていることが読み取れます。
以上、問いの本文を読み込んでくると、
設問アは、問い全体を読んで、そこにマッチするような「自分自身が携わった改修要望の分析」をまとめる。
設問イは、問い第二段落から4つの箇条書き部分にマッチするように「2.1.改善要望に対する情報収集(400字)、2.2.改善要望の分析(400字)、2.3.問題の真因特定(400字)」をまとめる。
設問ウは、問いの最終段落にある「解決手段・スケ・体制・投資効果」をからめながら「利用部門・関係部門との協議→対応方針の立案」をまとめる。
ということが分かってきます。
私の場合は、プロットまでは作らないにせよ、ざざざーと問い本文を一読して、問い2,3も同じように眺めて、どれを選択するかを決めるかな~と思います。万人に当てはめて時間がショートしてしまうと申し訳ないので、「私のやり方」と注釈の上、ちょっとフォント小さめにしておきます。
>>日経コンピュータ:定期購読
日経コンピュータの効用について、こちらにまとめました。
では、今回は、一旦、ここまで。先に問い2,3を考察してみて、余力があれば、実際に「自分が携わった」部分を、1.~3.にあてはめる更新をしてみます。皆さんも考えてみてください。
ではでは。試験対策、がんばりましょう!